Stranger in Spain (上)
<堀田善衛>を携えてゴヤを観にいく
2007年1月15日
 ▼2007年1月、バルセロナ・・・。
▼2007年1月、バルセロナ・・・。
これまで、いろんな路上パフオーマンスに出くわしてきたが、こんな手のこんだものは初めて見た。カオス、混沌、もっと大仰に言えば、近代の生みだした不条理と共に、その男はさかさまになって、微動だにしない。産み捨てられたあらゆるものを巻き込みながら雪崩うつ潮流の中に居る自分の存在を、一瞬に固定して、その男は血流さえも凝固さえ命がけで肉体を逆立ちさせている。
Stranger in Spain

 ▼21世紀初頭の日本を考える時、私の体内に最もしみじみ染みこんでくるのは、洪水のようにはき出される最新の論文でもエッセーでもない。作家・堀田善衛(1918年~89年) ▼21世紀初頭の日本を考える時、私の体内に最もしみじみ染みこんでくるのは、洪水のようにはき出される最新の論文でもエッセーでもない。作家・堀田善衛(1918年~89年)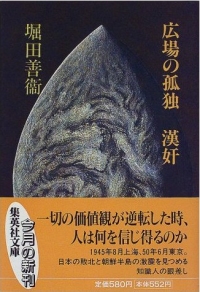 が50年前に書き下ろした「Stranger in Town=広場の孤独」だ。イラク戦争勃発後の混乱の中で、日本という国家は何にCommitしようとしているのか・・・それは、堀田が「広場の孤独」で描いた、朝鮮戦争という新たな戦争の渦中で、日本が国家をあげて国際社会にCommitすることに狂乱する様と何も変わっていない。 多くの戦後文学者たちが、15年戦争の残したあまりも大きな穴と格闘しつづける中で、堀田は雪崩を打ってやってきた「新たな戦争」を身体で受け止め固定して示した。それは、「思考停止」という「暗い穴」に陥った21世紀の日本人の心象風景そのものだとあらためて思う。 が50年前に書き下ろした「Stranger in Town=広場の孤独」だ。イラク戦争勃発後の混乱の中で、日本という国家は何にCommitしようとしているのか・・・それは、堀田が「広場の孤独」で描いた、朝鮮戦争という新たな戦争の渦中で、日本が国家をあげて国際社会にCommitすることに狂乱する様と何も変わっていない。 多くの戦後文学者たちが、15年戦争の残したあまりも大きな穴と格闘しつづける中で、堀田は雪崩を打ってやってきた「新たな戦争」を身体で受け止め固定して示した。それは、「思考停止」という「暗い穴」に陥った21世紀の日本人の心象風景そのものだとあらためて思う。
▼「広場の孤独」の先見性については、折りを見てまた考えるとして、今回のスペイン小旅行に、はガイドブックとして堀田善衛が1970年代をかけて描き上げた大作「ゴヤ」を持参した。ゴヤに執拗に寄りそい、時に「何故、こんな厄介な人物とつきあわなければならないのか。」と愚痴をこぼしながらも、長編が最後にさしかかりゴヤの最期を描く時期が近づくと「われわれの主人公の死の年が近づくにつれて、筆者の筆もまた重くなる。ありていに言って、書き進めたくないのである。長く、この我が儘で、しかも働きづめに働く芸術家の身に添って来て、その死にいたらねばならぬことは、やはり辛いことであった。・・・」と嘆いてみせる、あたりが可愛い(失礼)。
驚くべき旺盛な取材力と語学力でゴヤの残した絵の一枚一枚を訪ね歩き、資料を集め、読みとり、それらを自在に並べひたすらゴヤと併走することをめざした堀田善衛のジャーナリスト魂に圧倒され、敬服する。
▼今回の旅には、堀田善衛の「ゴヤ」を携えた。そして改めて、ゴヤに対する堀田の容赦ない観察に圧倒されている。以下は堀田善衛の「ゴヤ」をガイドに辿る、、拙い備忘録だ。
◇ カルロス4世家族図 ◇

▼広々としたプラド美術館で、ベラスケスの「ラス・メニーナス」の前にできた人の輪が次に移動するのは、ゴヤの「カルロス4世家族図」の前。スペイン国王とその一族を描いた縦2.8メートル、横3.36メートルの大作である。
作品が完成したのは1800年、ゴヤはこの時、54歳、首席宮廷画家だった。この絵を前に、堀田善衛は「近代への移行、あるいは近代そのものの誕生にわれわれは立ち会うことになるのである」と直截に定義した。
▼ゴヤは1746年3月30日、スペイン北東部の街サラゴサから南へ直線距離で35キロ、人口は当時100人余りのフエンデトードス(「みんなの泉」という語源を持つ)という小さな村で生まれた。その時、荒涼とした大地には乾いた寒風が吹きあれていたことだろう。堀田は初めて、ゴヤの故郷に足を踏み入れた時のことをこう書き残した。
 「サラゴサから石だらけの野を越え、また灰色の、石灰質の丘を越えてこの画家の生まれの村へ近づいて行くとき、この画家に強い関心を持った人ほど、なにかしら憂鬱な、しかも胸をしめつけられるような、暗い、ある意味ではまことに嫌な、来なければよかったというに近い感情に襲われるようである。 「サラゴサから石だらけの野を越え、また灰色の、石灰質の丘を越えてこの画家の生まれの村へ近づいて行くとき、この画家に強い関心を持った人ほど、なにかしら憂鬱な、しかも胸をしめつけられるような、暗い、ある意味ではまことに嫌な、来なければよかったというに近い感情に襲われるようである。
真夏ならば、大抵は35℃を越えている酷烈な陽光に焼かれなければならないし、冬ならばピレネーおろしの寒風にさらされなければならない。そうして雪もある。
車をとめて路傍の草花をでもつもうとすれば、大抵の植物にはトゲがあり、赤いケシの花でも、茎の高さはせいぜい15センチくらいしかのび得ないのである。・・・・」
ゴヤ初めての「自画像」1773年・27歳→
堀田は長編「ゴヤ」の冒頭に、ドン・キホーテの次の一節を掲げ、ゴヤを辿る長い旅を始めた。
「夏は堪えがたき日光に身をさらし、冬は針よりも鋭き氷雪をおかすのじゃ」
堀田とともにゴヤの長い人生路を辿り終えた読者は、このスペインの風土はゴヤの人生そのものだと深い感慨と共に悟ることになる・・・・

▼ゴヤの父親は、メッキ職人。教会や修道院などの金メッキの装飾の修理をしていた。サラゴサの修道会が経営する学校で学んだ少年ゴヤは、そこで画才を認められ、画家のアトリエへ弟子として迎え入れられる。立身出世のきっかけは結婚だった。妻の兄、フランシスコ・バイユーが、スペイン王室お抱えの宮廷画家をしていた。ゴヤは義理の兄を頼りマドリッドに昇り、以後、出世街道をかけのぼる。プラド美術館に飾られた、その頃の絵は無邪気で明るく、のびのびと陽光に溢れている。
ゴヤ「日傘」1777年↑
▼1789年、奇しくもフランス革命の年に、ゴヤは宮廷画家に任命される。このまま、なにもかも穏やかに進めば、ゴヤも宮廷画家として名前は残したかも知れないが、近代画家の創始者として語り継がれることもなかっただろうし、堀田がライフワークとして取り組む素材にもなりえなかったであろう。このフランス革命の年、ゴヤの人生は18世紀をまたいで、19世紀に突入した。
 ▼時代が大きく変動する時、その目撃者として、もっとも適した芸術家がこの世に送り込まれる。その白羽の刃がスペイン北部の寒村から成り上がった画家に当たったのだ。 ▼時代が大きく変動する時、その目撃者として、もっとも適した芸術家がこの世に送り込まれる。その白羽の刃がスペイン北部の寒村から成り上がった画家に当たったのだ。
「18世紀後半から19世紀の四半世紀、ゴヤの生きたスペインは、絶対王政(フランスならばアンシャンレジューム)の崩壊から革命(スペインでは本当の意味でこれがなかった)を経て近代国家へと脱皮するのに失敗、20世紀のスペイン内戦にまで連なる分裂と混迷とが生み出された。王権と国家、キリスト教と教会という二大体制が崩れゆく中で、ある者は旧体制の復活を夢に、ある者はゴヤのように、自由と革命に希望を託する。そうしてこの二つのスペインの間で、弾圧と迫害、反乱と暴動、また民衆と愚妄と狂気も渦巻くのである。」(「かくして、ゴヤは近代への扉を叩く」<大高保二郎・ゴヤの巻末エッセイより>
↑ゴヤ「巨人」1810ー12
プラド美術館

▼御しようもないカオスの穴にスペイン全土が呑み込まれていくこの時期、首席宮廷画家にまで上り詰めたゴヤの肉体は奈落の底に突き落とされる。皮肉なことにベートーベンと同じ46歳という年齢で、ゴヤは全聾に至る重病に襲われる。この絶望の淵に立った鋭利なゴヤの感性と、とらえどころのない巨大な時代のうごめきが、見事に共鳴し震えおののきはじめた。そして、その後、ゴヤから絞り出され続けたスケッチの一片一片までを丁寧に辿りつづけた堀田も、ゴヤと時代の振り子とともに、共振しつづけたのだろう。堀田の原点、「広場の孤独」のブックカバーの言葉が浮き上がる。
「一切の価値観が逆転した時、人は何を信じうるのか?」
聴覚を失った直後の自画像1795-97 ↑
 ▼もう一度、「カルロス4世家族図」の前に立とう。この作品が完成したのは1800年。作品に取りかかる時、ゴヤはすでに音のない(もしくは怪音が頭蓋骨の中を響き渡る)世界にいる。ゴヤはあのベラスケスに倣うように、画面の隅の闇の中に配している。首席宮廷画家としては、浮かぬ顔のように見える。堀田も何度も言及しているが、ゴヤは不思議な男である。首席宮廷画家になってから、王室のために描いた絵はこの「カルロス4世家族図」一枚だけである。 ▼もう一度、「カルロス4世家族図」の前に立とう。この作品が完成したのは1800年。作品に取りかかる時、ゴヤはすでに音のない(もしくは怪音が頭蓋骨の中を響き渡る)世界にいる。ゴヤはあのベラスケスに倣うように、画面の隅の闇の中に配している。首席宮廷画家としては、浮かぬ顔のように見える。堀田も何度も言及しているが、ゴヤは不思議な男である。首席宮廷画家になってから、王室のために描いた絵はこの「カルロス4世家族図」一枚だけである。
「たった一枚!それはたしかに大作である。しかしたった一枚だけ、とは。後年フエルナンド七世ノ肖像を描いている。けれどもそれは宮廷の用命によるものではない。民間からの注文仕事であった。
まったく仕事をせずに、その称号と五万レアール(約1万2500ドル)の年俸と馬車その他の費用若干と公邸をもらいつづける。それは誰にもできる芸当ではない。ではその理由は何だったのであるか?それがよくわからない」
(堀田善衛「ゴヤⅡマドリード・砂漠と緑」)
 ▼首席宮廷画家が王室のために描いた、たった一枚の肖像画。その中央に堂々と立つのは国王ではない。王妃のマリア・ルイーサである。自慢の太い腕を際だたせ、「この一族は私が仕切っているのよ」という、いでたちからはその性格が見事にみてとれる。王妃に対する堀田の描写も手厳しい。 ▼首席宮廷画家が王室のために描いた、たった一枚の肖像画。その中央に堂々と立つのは国王ではない。王妃のマリア・ルイーサである。自慢の太い腕を際だたせ、「この一族は私が仕切っているのよ」という、いでたちからはその性格が見事にみてとれる。王妃に対する堀田の描写も手厳しい。
「王妃のマリア・ルイーサは、これはもう鼻持ちならぬ女悪党であった。しかし私自身は別にこの王妃の臣下でも何でもないの であるから公平を期するとして、とにかく欲の皮がつっぱった、これが欲しい、あれが欲しいとなったら、土地でも、恋人でも、宝石でも、それはもうど であるから公平を期するとして、とにかく欲の皮がつっぱった、これが欲しい、あれが欲しいとなったら、土地でも、恋人でも、宝石でも、それはもうど こどこまでも頑張り通して手に入れる。これを善意に解するとすれば、意志の強い女性であった、と言えるであろう。この意志の強さが欲の皮の方へではなくて、それを抑制する方向に働いていたとしたら、およそ決定ということを一切しない、したくない夫を助けて夫の父の王の名を辱めない働きをしたものであったかもしれない。 こどこまでも頑張り通して手に入れる。これを善意に解するとすれば、意志の強い女性であった、と言えるであろう。この意志の強さが欲の皮の方へではなくて、それを抑制する方向に働いていたとしたら、およそ決定ということを一切しない、したくない夫を助けて夫の父の王の名を辱めない働きをしたものであったかもしれない。
大体この女性、パルマ公国の公女として生まれていて16歳の皇太子カルロスと13歳のときに結婚をしたもので、婚約が整った瞬間から、もう家中でも未来のスペイン王妃としての、ひさわしい敬意を払うように、と要求して兄弟姉妹の間で喧嘩が絶えなかったというのであるから、はじめから絶望であったものかもしれない。」(ゴヤⅡより)
▼王妃に中心の座を譲っても、王は意に介していない風情である。カルロス4世は、善良で、信心深く、かつ愚鈍な男であった。体力が自慢で威風 堂々としていたが、政務には全く無関心で、毎朝、天候はどうであれ、早朝から狩猟にでかける日々を繰り返した。その生活のリズムは、スペイン王国とその王冠の運命が危機に瀕しても、変わらなかった。 堂々としていたが、政務には全く無関心で、毎朝、天候はどうであれ、早朝から狩猟にでかける日々を繰り返した。その生活のリズムは、スペイン王国とその王冠の運命が危機に瀕しても、変わらなかった。
「こういう夫では、妻が死ぬほど退屈をしても仕方がない。28歳あたりの時から自分で自分の生活をすることに決めたようである。はじめの若いツバメは、後にゴドイの副官になるモンテイーホ家のテバ伯爵であったらしく、次なる男はピニアレルリ家の若いフエンテス伯爵、この後者は、アルバ公爵夫人に寝取られてしまって、これがあとあとまでつづく王妃の側の怨恨のもととなる。その次がポルトガル王家のランカストレ伯爵、廷臣のオルティス伯爵、そうしてマヌエル・ゴドイが来る・・・・」(ゴヤⅡ)
▼次々の男妾(メカケ)を持った王妃が最も入れ込んだ男が、マヌエル・ゴドイだ。18歳の時、近衛兵として34歳の王妃に見初められ、たちまち昇進をさせてもらって将軍になり、25歳で総理大臣となった。スペイン王国の政務は国王夫妻ではなく、このゴドイにまかせぱなしにされた。
▼しかも、このゴドイという男も性欲の塊だった。
「このときのスペイン宮廷は、あるフランス人が“宮廷女郎部屋”と呼んでいるほどに非道いことにねっていた。王妃を愛人としてもちながら、ゴドイは次から次へと女を、宮廷内の総理執務室の別室へ引き込み、公然として特定のメカケまでをもっていた。王妃が怒って総理執務室へ怒鳴り込めば、ゴドイはこの王妃を殴り倒して平然としていた。それでも王妃マリア・ルイーサはゴドイに夢中なのである。」(ゴヤⅡ)
 ▼左の絵は「カルロス4世家族図を描き上げた翌年にゴヤが描いたマヌエル・ゴドイ像である。「カルロス4世家族図」に描かれた子供達の中にも実は王妃とゴドイの間に出来た子もいる。家族図の後ろではこの男が君臨して荒ぶれていた。 ▼左の絵は「カルロス4世家族図を描き上げた翌年にゴヤが描いたマヌエル・ゴドイ像である。「カルロス4世家族図」に描かれた子供達の中にも実は王妃とゴドイの間に出来た子もいる。家族図の後ろではこの男が君臨して荒ぶれていた。
「その品行は・・・・これはもう愛人であり保護者であった王妃同様に、無茶苦茶であった。精力がありあまっていたのであろう。1801年にゴヤは“オレンジ戦争”と呼ばれたポルトガル征伐に完勝を得たゴドイの代償像を大肖像画を描くのであるが、そこに元帥服を着てだらしなく長椅子に腰を下ろした青年元帥は、赤ら顔に肉付きのよすぎる体躯を見せて、その好色さ加減を十全に表現している。
戦勝祝賀の図が、戦勝や戦功などよりむしろこの男の好色さ加減を表現するとは・・・」
 (ゴヤⅡ) (ゴヤⅡ)
▼また、横道にそれてしまった。「カルロス4世家族図」に戻る。堀田の解説を聞きながら、観賞することにしよう。
「右の、王との間にいる赤い服の男の子は、ドン・フランシスコ・デ・パウラ・アントニオ親王で、ゴドイとのあいだの子供だと言われている。六歳。・・・・王妃の左は、ドーニャ・マリア・イサベル、この子もゴドイとのあいだの子という噂があった。が、噂のことはとにかくにもして、この子は母親に実に酷似している。十一歳。この二人の子供達だけは、子供を描く場合にはいつもそうであるように、ゴヤの愛情を受けている。」

「左端がドン・カルロス・マリア・イシード殿下。十二歳。この子も、ここに登場している王族の全体にとって何がどうなっているのか一切理解出来なかったであろう十九世紀というものに翻弄され、1855年にベネチアの対岸トリエステで死ぬ運命にある。」
「次が皇太子、八年後に、ほかならぬこのアランホエース離宮で父に対して謀反を起こしてフエルナンド七世を名乗り、父母とゴドイともどもにナポレオンにバイヨンヌまで呼びつけられる。ここで母のマリア・ルイーサに、ナポレオンの面前で、“この私生児めが!”と怒鳴り付けられるのであるが、だれを父とする私生児なのかはわからない。十六歳」
「次、鳥のフクロウか何かのような顔だけをのぞかせているのがカルロス4世の姉、ドーニヤ・マリア・ホセーア、五十六歳。右目の横に黒いものを張っているのは、化粧黒子なのか、それとも丹毒をでも病んでいるのか、わからない。・・・」
「その右隣りの、完全にそっぽを向いている内親王が何者であるか、何しろ顔がわからないのだから始末におえない。二説ある。
一つは、カルロス四世の長女のドーニャ・カルロータ・ホアキーナであろうといわれる。・・・・・第二説は、やがて、二年後に皇太子の嫁に来るはずのナポリ女王の娘マリア・アントニアであろうと言う。それが来てから、このそっぽを向いた顔をこっちへむけて書き直すはずであった、というのである。
▼19世紀の到来とともに、スペインは、欧州は、世界は一気に怒濤と共に戦乱の時代へと突入する。その渦中、まさに18世紀最後の年に、首席宮廷画家は、絶対王政が崩壊直前に辿り着いた最期の姿をとらえてみせた。それは、悦楽と欲望と嫉妬が渦巻く矛盾にみちた歪な王室の姿だった。首席宮廷画家が描き出したその表情の一つひとつに外界から完全に孤立し彷徨う漂流者の体臭が充満している。画家自身も、自らをその空間に配した。かつて師ベラスケスが、国王の玩具となった自らの姿をその中に配したように。ゴヤもkの宮廷という閉ざされた世界で欲望の限りをつくした。聴覚を失うというどん底の日常の中で、ゴヤは屈折した重いと共に自分をカルロス王家の人々と同じ空間に配したにちがいない。カルロス王家とゴヤの乗る漂流船には、弾圧と迫害、反乱と暴動、愚妄と狂気が渦巻く暴風雨がすぐそこまで迫っている。
 「チャーチル風に言うとすれば、かくも美しい衣装をまとい、金銀宝石に飾られていて、しかもなお資性愚鈍かつ低劣な人間群衆をかつて見たことがない、とでもいうことになるであろうか。」 「チャーチル風に言うとすれば、かくも美しい衣装をまとい、金銀宝石に飾られていて、しかもなお資性愚鈍かつ低劣な人間群衆をかつて見たことがない、とでもいうことになるであろうか。」
「身心ともに病み、衰え、退廃し、ぶよぶよの水ぶくれになり、要するに十三人すべては、すでに終わった人々、生きながらにして、たとえばエル・エスコリアール離宮内の、死体の腐らせ場に立っている人々である。
それは中世から数百年にわたって持続してきた、一時代の死である。
十四人目の人としてのゴヤは影に沈んで、Yo lo vi 私がこれを見た、と呟いている。
一時代の死という不吉なものが、かくも絢爛豪華な意匠をまとって描かれたことは、人類が持つ長い絵画の歴史にも絶無であった。
しかもこの大画面を、たとえばルーブル美術館の大壁面を占領している、ゴヤの同時代のダビドの手による「ナポレオン皇帝戴冠式図」なるものと比べるとき、ゲーテならずとも、われわれは果たしてどのような時代がこのあとに来るものであるかを、すでに予言されている。本質的に十八世紀の人であるゴヤは後ろ向きに、背中の方からこの全的に新しい時代に入って行く。」 <堀田善衛「ゴヤⅡマドリード・砂漠と緑」より>
▼初めてプラド美術館で巨大な実物を前にして、思ったことがある。それは、カルロス王家の人々の後ろで、キャンバスに向かうゴヤが何を描こうとしているのか、それが肖像画だとして誰を描 こうとしているのか、ということだ。 こうとしているのか、ということだ。
私は、それは次の年に実際に描き上げることになるマヌエル・ゴドイに違いないと確信した。王妃を手込めにし王室を食いものにしたこの男の色欲・出世欲はやがて戦争という巨大な欲望の穴に吸い込まれていく。この時期、ゴヤが熱愛したアルバ公爵夫人をもゴドイは寝取った。その若き権力者の暴走にたいして、聴覚を失った54歳のゴヤは、狂おしいほどの屈折した思いで向き合っていたのではないか。そのことがまもなく「着衣のマハ」「裸のマハ」を生み出す起爆剤となる。


▼そして、ゴヤの後ろに掲げられている巨大な二枚の絵、まずその右側に掛けられている風景画、それは1810年にゴヤが描き上げることになる「巨人」」の背景ではないか。荒涼とした大地の空に出現した「巨人」が豆粒のような民衆を背にして、彼らの意を受けて何者かに立ち向かうべく巨大な力、「巨人」は来るべき暴力の時代に抗して戦う、という民衆の宣言でもある。そのその下絵が右の絵である。
さらに、左の真っ黒なキャンバス、これこそ、晩年、一人暮らしの彼の部屋の四方壁に掲げられた「黒い絵」ではないか。この二つの作品は、依頼されたものでなくゴヤが自分のために描き上げることになる絵である。ゴヤは背後に、やがてくる自分の運命までを描き込んだのだ。
これはあくまでも、勝手な思いこみだ。実物の前に来ると不思議なオーラに圧倒されて、いろんな妄想に囚われる。そこが面白い。
Yo lo vi 私がこれを見た <ゴヤ>
つづく
※絵画引用は、Francisco de Goya Onlineから世界各地の公共美術館からさせていただきました。営利活動に使うことは一切ありません。
|