K・N氏からの便りジャズの話をしよう⑧
マイルスの同行者 “神秘”
Wayne Shorter
2007年9月27日
“Very
Special One-time Performance”、 V.S.O.P.がやってくる。
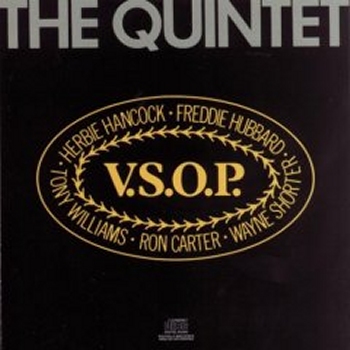 ◇“The Quartet”。 ◇“The Quartet”。
定冠詞をもって名づけられたこのバンドはウェイン・ショーター(Saxophone)、ハービー・ハンコック(Piano)、ロン・カーター(Bass)、そしてジャック・デジョネット(Drums)のユニットだ。 全員があのトランペッター、
マイルス・デイビスの遺伝子を受け継ぐジャズ・ミュージシャンである。
2007年10月、“生きる伝説”が新たに日本でスタートする。
建国から200年、ジャズというアメリカが生んだ偉大な芸術の祝祭の年、1976年、V.S.O.P.は当初、たった一度の演奏のため結成された。ウェインやハービー、ロンと共にステージに上がったのはフレディ・ハバード(Tp)、トニー・ウィリアムス
(Drums)。かつての仲間たちが思い描いたトランペッターは、紛れもなくマイルス・デイビスであった。
マイルスのため席を暖め、待っていた彼ら。しかし、暗闇の世界に身を沈めていたマイルスは、高弟たちの求めに応ずることもなかった。
◇ 1979年7月26日、「田園コロシアム」で行われたV.S.O.P.のライヴは、伝説となって語られている。
「田園コロシアム」、通称「デンコロ」は東京・田園調布の閑静な住宅街にあった多目的屋外スタジアムである。戦前の1936年オープンし50数年の後、その役割を終えている。
演奏の素晴らしさはもとよりだが、二日ほど前、梅雨明けを迎えた東京の、その「デンコロ」を襲った局地性の豪雨は、この夜のドキュメンタリー性をいっそう高めている。コンサートはハービーのオリジナル、“The Eye Of The Hurricane”で幕を開け、一期一会の演奏は、雨をもエネルギーへと変えていった。素晴らしいのは、トニーのドラムスだ。バンド全体に高揚を与え、全員のクライマックスを提示している。
トニーについて、こんな逸話が残っている。“60年代、マイルスはまるで雷鳴のようなトニーの激しいプレイに心酔していた。サウンド・チェック中のエンジニアから、ドラムのボリュームを下げてもいいだろうか、と訊ねられるたびに、マイルスは「やつの好きにさせておけ。」と半分脅すような口調で言ったという。”
マイルスは17歳のトニーの才能を見出し、栄光あるマイルス・バンドの一員に招いた。彼はことあるごとにトニーを褒めちぎっている。それほどまでにトニーは素晴らしい。
 私の友人ヨシオ君は、その夜、V.S.O.P.の演奏を間のあたりにしている。後年、彼はプロのドラマーとなるが、トニーは彼の最大のアイドルであった。トニーの疾風怒涛のような演奏は、ジャズの楽器編成の概念を超えた。トニーの演奏がメンバーを鼓舞し、トランペットなど、フロントに出ていた楽器までもが追従する。だとしたら、ウェインもハービーもロンも、そしてマイルスさえもあの若者が放つ音に、必死になってついていったに違いない。 私の友人ヨシオ君は、その夜、V.S.O.P.の演奏を間のあたりにしている。後年、彼はプロのドラマーとなるが、トニーは彼の最大のアイドルであった。トニーの疾風怒涛のような演奏は、ジャズの楽器編成の概念を超えた。トニーの演奏がメンバーを鼓舞し、トランペットなど、フロントに出ていた楽器までもが追従する。だとしたら、ウェインもハービーもロンも、そしてマイルスさえもあの若者が放つ音に、必死になってついていったに違いない。
その、もういなくなったトニーから、今回ドラムスの役割を引き継いだジャックは、マイルスの不朽の名作、“Bitches Brew”で複合的なリズムを示し、以来数年間マイルスを支える。
 V.S.O.P.の全員が一つの塊となる。圧倒的な存在感を示し、その演奏はモダン・ジャズの魅了とエッセンスに満ちている。途中、ハービーは“Beautiful! Wayne”と、仲間を臆面もなく称えている。マイルスの永遠なる継承者たち、全員が美しい。 V.S.O.P.の全員が一つの塊となる。圧倒的な存在感を示し、その演奏はモダン・ジャズの魅了とエッセンスに満ちている。途中、ハービーは“Beautiful! Wayne”と、仲間を臆面もなく称えている。マイルスの永遠なる継承者たち、全員が美しい。
◇“The Eye Of The Hurricane”は、ハービーのリーダー・アルバム、“Maiden Voyage”
(処女航海)に納められている。
 1965年に録音されたこの演奏は、ハービーにとって大きなステップとなった作品だが、私にとっても大きな思い出となっている。ハービーのオリジナル、5曲全てが“海”にちなんでいる。そして彼はライナー・ノーツに、海の持つ威厳、輝き、美しさを書き残している。 1965年に録音されたこの演奏は、ハービーにとって大きなステップとなった作品だが、私にとっても大きな思い出となっている。ハービーのオリジナル、5曲全てが“海”にちなんでいる。そして彼はライナー・ノーツに、海の持つ威厳、輝き、美しさを書き残している。
オリジナル演奏は、ミディアム・テンポの中、ゆったりと響いている。冒頭の“Maiden Voyage”からラスト・トラックの“Dolphin Dance”に至るまで、新進気鋭のピアニスト、ハービーは時代のムードを奏でている。モダン・ジャズの巨匠、バド・パウエル直系の4ビートのフレーズ、モーダルな響き、時折垣間見せる不協和音。すべてはレコード・エンジニア、ルディ・ヴァン・ゲルダーの手によって魅力的なブルー・ノート・サウンドに仕上がった。
新主流派と言われた仲間たち、フレデイのトランペットや
ジョージ・コールマンのスタイリッシュなテナー・サックスの響き、彼らの演奏は当時のジャズの最先端を、伝統に根ざした形で発散している。
◇青春の思い出を披露したい。“処女航海”とともに甘酸っぱい記憶が蘇る。
1971年夏、母校の学園祭を前に、我が家で演奏に励む2人の青年と1人の少女。ベースのナベさんがどこからか誘い入れたのか、ピアノはある女子校のヤチヨさんである。「オスカー・ピーターソンばりのピア二ストがいる・・・。」無論、ピーターソンとはいかなかったが、ヤチヨは力強いタッチで我が家のピアノを弾いていた。
北国の終わり行く、ある夏の日の昼下がり、ピアノを囲み演奏する3人。彼らの演奏を隣の室で聴く。一緒に耳を傾けるのは、見も知らぬ2人の少女。ヤチヨが連れて来た女の子は、ちょっと舌足らずで甘い声の「ルー」と、お姉さん風の「タクミ」。彼女たちは、同級生にはない匂いを発散していた。ロング・スカートのセーラー服、うっすらとした化粧、親しげな話し口・・・。コーヒーを入れ、精一杯背伸びをしながら、迷い込んだような子猫たちに、ピーターソンやハービーを語っていた当時の私。
ナベさんは後年、ピアノの調律師の道を選び、故郷で活躍している。ドラムスのヨシオ君は音楽家となった。ヤチヨは銀座の片隅でクラブを経営し、今も時折ピアノを弾いている。
◇V.S.O.P.はマイルスのカム・バックを祈って結成されたバンドである。ジャズ・シーンから忽然と姿を消した直後の1976年、ハービーはウェインやロンそしてトニーとともに、マイルス・デイビス・クインテットの再現を企てる。マイルスから再び霊感を求めたい・・・。
“The Eye Of The Hurricane”で始まる演奏はハービーとウェインのデゥオ“Stella By Starlight”、そして間断なく続く“On Green Dolphin Street”で幕を閉じた。終演を告げるアナウンスにもかかわらず、演奏されたジャズのスタンダード。イントロでのハービーのピアノ・ソロ、その音に誘われるウェインのテーマへのつながり。名曲は当代一流の彼らによって見事に再生されている。“豪雨”により、主客一体となった演奏は私の中、より遠景へと、“音”のデジャ‐ビュとなってつながっている。
その音とは有名なマイルスの“Stella By Starlight”の演奏。
1964年、リンカーン・センター・フィルハーモニック・ホールでのライヴ。リズムがそれぞれのテンポを刻み、マイルスのソロが移りゆく中、ホールに響く観衆の雄叫び。主客一体と言えば、あのマイルス・デイビス・クインテットの演奏の中、思わず叫んでしまった一人の心の発露に思いは至る。
音から音へとつながるそれぞれの風景が、色彩豊かに私の中、万華鏡となって映し込まれている。
1979年、V.S.O.P.の演奏の後、ウェインは述懐している。「われわれの方も感動したよ。何と言っても、あの雨だからね。でも、雨のおかげ、と言っては何だけど、我々と聴衆とが本当に一体になれたと思う。一体となって“雨に勝ったぞ”という感じだった。ああいう素晴らしいコンサートの時は、こちらも疲れなんて感じなくなるよ。映画じゃ、ああいうシーンは撮れないね。」
◇当時のジャズ・シーンを俯瞰すれば聴衆はストレート・アヘッドなジャズに飢えていた。1969年、マイルスの“Bitches Brew”以降、モダン・ジャズはエレクトリックと、複合的なリズムの真っ只中にあった。それはマイルスが示した方向であり、時代の先端はそこにあった。しかし、かつてのマイルス・デイビス・クインテットへの憧憬は根強いものがあった。V.S.O.P.は必然となって豪雨の中、「デンコロ」で演奏する。
◇振り返るとエレクトリックと、複合的なリズムの発展形が“WEATHER REPORT”である。彼らの実験的とも思える音楽。一方“V.S.O.P.”に代表される新主流派の古典。その両方に身を置き、それぞれに神秘をたたえているのがウェイン・ショーターである。
◇ウェインは50数年にも亘りジャズ・シーンを牽引し、今尚大きな影響力を示している数少ないミュージシャンだ。1960年代後半、ウェインはマイルスに大きな影響を与え、マイルス・バンドはウェインの色に染まっていく。ジャズの改革者、ジョ ン・コルトレーンの影響を大きく受けながらも、自己のスタイルを確立したウェイン。幻想的で神秘的なまでの彼の音楽は伝統と進取に踏まえたものである。 ン・コルトレーンの影響を大きく受けながらも、自己のスタイルを確立したウェイン。幻想的で神秘的なまでの彼の音楽は伝統と進取に踏まえたものである。
ウェイン・ショーター。1933年8月25日、アメリカ、ニュージャージー州ニューアークに生まれる。ニューヨーク大学で音楽教育学を専攻したウェインは1959年、ジャズ・バンドの名門、アート・ブレーキー・ジャズ・メッセンジャーズに迎え入れられた。1964年から70年まで、マイルスのバンドに在籍。1960年代初頭、モード・ジャズで新たな方向を指し示したマイルスは、しばしライヴでの演奏に没頭する。そして新しいチャレンジへのパートナーを見つける。それがウェインであった。マイルスは再びクールなグループ・サウンドを追及していく。そしてウェインはマイルス・バンドのミュージカル・ディレクターとして重要な役割を演じた。彼らの共同作業のひとつの頂点が1967年発表のマイルスのアルバム、“Nefertiti”である。マイルスのオリジナル曲が一曲もない“Nefertiti”こそ、“Esp”以来のスタジオ録音による、二人のコラボゼーションの結実となっている。
「Foot(フット) Prints(プリンツ)~評伝ウェイン・ショーター~」にこんな記述がある。
 “1967年のある夜、彼は自室でろうそくに火を灯すと、ピアノの前に座った。鍵盤の上に両手を乗せた瞬間、ある曲の完全なメロディーがふと浮かんできた。ウェインがニュー・アーク・アーツ・ハイ・スクール時代、彫刻で作ったエジプト王妃「ネフェルティティ」の胸像は、卒業からしばらく経った1967年当時も、学校のロビーに誇らしげに飾られていた。学生時代、この胸像を無から創設した時と同じく、彼は「ネフェルティティ」のメロディを自室の暗闇の中で、まるで彫刻するように書いたからだ。” “1967年のある夜、彼は自室でろうそくに火を灯すと、ピアノの前に座った。鍵盤の上に両手を乗せた瞬間、ある曲の完全なメロディーがふと浮かんできた。ウェインがニュー・アーク・アーツ・ハイ・スクール時代、彫刻で作ったエジプト王妃「ネフェルティティ」の胸像は、卒業からしばらく経った1967年当時も、学校のロビーに誇らしげに飾られていた。学生時代、この胸像を無から創設した時と同じく、彼は「ネフェルティティ」のメロディを自室の暗闇の中で、まるで彫刻するように書いたからだ。”
1967年6月7日、マイルスのレコーディング・セッションにウェインはこの曲を持参した。トニーのダイナミックが時とともに増し、マイルスとウェインが一つのフレーズを繰り返していく。そして、リズム・セクションがトルネードとなり絶頂を迎える。ジャズの一つの古典的様式がそこにある。マイルスは後年、「ウェインはいつも様式を使って実験する男だった。様式なしで実験的なことをする連中とは違っていた。」さらに続ける。「だからこそ、オレがプレイする音楽の行方を見させるのに、あいつなら完璧だと思ったんだ。」

我が家の愛犬はティティ、ネフェルティティという。2年前の5月29日生まれのメスのミニチュア・シュナゥザーだが、その年の8月、彼女は私たちに幸を恵むべく、生まれたばかりの体をあずけた。皆で名前を考えた。様々な候補が行き交う中、世界史好きな息子が提示したのが「ネフェルティティ」であった。当時、高校3年生の彼がこれしかないと言う名前が「ネフェルティティ」である。
ウェインの“Nefertiti”を知る由もない彼は、薀蓄を垂れる。古代エジプトの王妃、「ネフェルティティ」は歴史上名高いあの「ツタンカーメン」の義理の母親で、エジプト南部の地から嫁入りしたのだという。その名の由来は“美しきもの来たる”。息子の提案を即座に受け入れた私たちは、子犬に「ネフェルティティ」という名を授けた。あの時の子犬は今、ジャズの歴史に色濃く刻まれた“美しき音楽”、“Nefertiti”の響きを体いっぱい発散している。
 ◇ウェインがその才能を開花させたマイルス・デイビス・クインテット。自己のオリジナル曲名ともなっているウェインの“フット・プリンツ”は、単なる足跡では済まされない多くのものを残している。ハービーはこう評している。「ウェイン・ショーターはジャズの全ての歴史を総合して、それをきわめて特別な、きわめて生き生きとした音楽的表現に代えることが出来る。今、そんなことが出来るのは、彼を置いて他にいない。」
◇ウェインがその才能を開花させたマイルス・デイビス・クインテット。自己のオリジナル曲名ともなっているウェインの“フット・プリンツ”は、単なる足跡では済まされない多くのものを残している。ハービーはこう評している。「ウェイン・ショーターはジャズの全ての歴史を総合して、それをきわめて特別な、きわめて生き生きとした音楽的表現に代えることが出来る。今、そんなことが出来るのは、彼を置いて他にいない。」
ハービーの言葉を借りるまでもなく、ウェインの辿ってきた道は、アメリカ音楽の壮大な物語である。ビー・バップからハード・バップ。マイルスとのコラボレーション。ジャズ・レーベル、ブルー・ノートに残されている緒作。“WEATHER REPORT”に代表されるジャズの進化。ブラジリアン、ミルトン・ナシメントとの遭遇。フュージョン。彼の道はアメリカ音楽の凝縮でもある。
◇マイルスとの出会いに敷衍する。1965年、マイルスは後年の音楽をイメージして、クインテットを結成した。不動のスリー・リズムに対しテナー・サックスはコールマン、サム・リヴァース、そしてウェインへと移っていく。ウェインのマイルス・バンドでの最初の録音がベルリンでのライヴとして残されているが、ウェインの影響は何も感じられない。大きく変わったのが1965年1月録音の“Esp”からである。マイルスは常に何かをメンバーに課した。“Esp”から“Nefertiti”に至るまで、メンバーのオリジナリティを最大に尊重するマイルス。その直後のエレクトリックの洗礼とポリ・リズムのうねりを前に、彼は何と静謐な音楽を私たちに示したのであろう。後年、ブラック・ミュージックの矜持を示した“Bitches Brew”から“On The Corner”、更には路上の音楽、ヒップ・ホップに触発された“Doo-Bop”に至るまで、マイルスの“フット・プリンツ”は過去の全てを糧とする作業に他ならない。
“Bitches Brew”のわずか半年前、控えめなエレクトリックとポリ・リズム。一定調和のリズムの元、マイルスは“In A Silent Way”を世に問うた。アルバム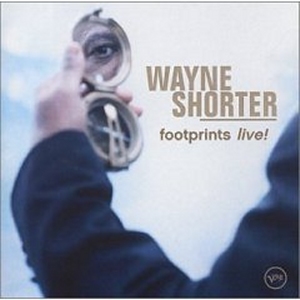 ・タイトルともなっている“In A Silent Way”は、ピアニスト、ジョー・ザヴィヌルのオリジナルである。当時牧歌的とも評されたこの作品は、ウェインのソプラノ・サックスが大きくフイチュアーされている。続く“IT’About That Time”、いきなり8ビートのロックのリズムに乗り、マイルスのトランペットは、我々を抽象の世界へと誘う。ジョーは“Bitches Brew”で再び自己のオリジナル、“Farao’sDance”を提供している。“In A Silent Way”で示した静謐な世界とは対照的に、煽情なまでのエレクトリック・ピアノが全員に音楽的高まりを投げかけている。アルバムの中、左右のチャンネルから響くチック・コリアとジョーのピアノ。二人はマイルスの元、限りない緊張を保ちながら、創作をなしている。そして“Bitches Brew”の最後を飾るウェインのオリジナル、“Sanctuary”は、“Nefertiti”同様、マイルス以下全員がねじりあい、終わりへと向かっている。 ・タイトルともなっている“In A Silent Way”は、ピアニスト、ジョー・ザヴィヌルのオリジナルである。当時牧歌的とも評されたこの作品は、ウェインのソプラノ・サックスが大きくフイチュアーされている。続く“IT’About That Time”、いきなり8ビートのロックのリズムに乗り、マイルスのトランペットは、我々を抽象の世界へと誘う。ジョーは“Bitches Brew”で再び自己のオリジナル、“Farao’sDance”を提供している。“In A Silent Way”で示した静謐な世界とは対照的に、煽情なまでのエレクトリック・ピアノが全員に音楽的高まりを投げかけている。アルバムの中、左右のチャンネルから響くチック・コリアとジョーのピアノ。二人はマイルスの元、限りない緊張を保ちながら、創作をなしている。そして“Bitches Brew”の最後を飾るウェインのオリジナル、“Sanctuary”は、“Nefertiti”同様、マイルス以下全員がねじりあい、終わりへと向かっている。
“Bitches Brew”セッションの後、ウェインと妻・アナ・マリア・パトリシオとの間に長女が生まれた。子供は「イスカ」と名づけられた。
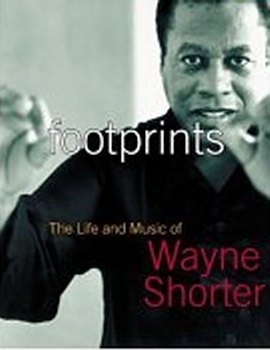 「Foot Prints~評伝ウェイン・ショーター~」は、このように記述している。 「Foot Prints~評伝ウェイン・ショーター~」は、このように記述している。
“ウェインはナイジェリアの作家、シプリアン・エクスタシーの小説「イスカ」を愛し、独立のアフリカを席巻した変化の風の象徴である主人公の少女、「イスカ」に敬意を抱いていた。「イスカ」とはハウサ語で“風”を意味し、詩や小説では“変化”あるいは“幽霊”のような異世界との境にいる存在を表す言葉としても使われていた。”
イスカは生まれてまもなく脳の障害を負い、1983年、14歳で帰らぬ人となる。後年会ったウェインは、私に穏やかな眼差しを投げかけていた。イスカとアナ・マリアの悲劇、深い悲しみを知る者だけの眼差し・・・。
ブルー・ノートの作品“Super Nova”、“Odyssey Of Iska”、そして“Moto Grosso Of Feio”は1969年から70年にかけ記録されている。これらの諸作の様々は、過ぎ去った風のようにも聴こえる。
“Odyssey Of Iska”のライナー・ノーツは冒頭と終わりに、「“Iska ”は通り過ぎる風、跡形もなく消えゆく。」というウェイン自身のフレーズが書き残されている。
愛しい娘の悲劇を、この時彼は暗示している。
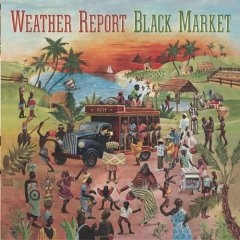
ウェインの思惑とはうらはらに、ジャズ史上、最大の商業的成功を収めた
“WEATHER REPORT”(W.R.)は、1970年の暮れ、ジョー・ザヴィヌル、そしてベースのミロスラフ・ヴィトウスと一緒に結成したバンドである。3人は精神的結びつきを果たし、マイルスの世界の発展形を構築しようとしていた。このバンドの衝撃は今も大きく語り継がれている。スリー・ヘッド・バンドとしてスタートしたW.R.は、ドラムスのアルフォンズ・マウゾン、パーカッションのアイアート・モレイラとバーバラ・バートンらがそれぞれと等距離を保ちながら、演奏にしのぎを削っていた。凝縮力はすさまじい。

ジョー・ザヴィヌルは1932年、オーストリアのウイーンに生まれる。7歳からウイーンの音楽学校で学んだ後、アメリカ・ボストンのバークレイ音楽院に進む。1962年、キャノンボール・アダレイのクインテットに参加、ジョーのオリジナル、“Mercy・Mercy・Mercy”は1967年のグラミー賞を受賞。改めてだがマイルスのアルバム、“In
A Silent Way”や“Bitches Brew”に大いなるアイディアを与えた。
ミロスラフ・ヴィトウスは1947年、チェコ・スロバキアに生まれる。プラハの音楽学校でクラシックの作曲法を学んだ後、ジョー同様、バークレイ音楽院で学ぶ。70年にはジャズ専門誌、ダウ ンビート誌の投票でNo.1ベーシストとなり、“ Infinite Search”で衝撃的なデビューを果たした。そしてウェインやジョーとともに、マイルスのレコーディングに参加する。 Infinite Search”で衝撃的なデビューを果たした。そしてウェインやジョーとともに、マイルスのレコーディングに参加する。
攻撃的でもあり叙情的なサウンド。W.R.の出現により、ジャズはアドリブよりも、グループ全体としての表現が重要になっていくと言われていた。そのとおり、彼らの音楽は指導者のいない共同体にある。メンバー一人一人が、創造性とインスピレーションを示し、誰もが他のメンバーと融合(フュージョン)している。そして二律背反する“攻撃的でもあり叙情的な”というモチーフ、W.R.は見事に同居させた。
1972年、新年早々の来日公演、その時のパンフレットにアメリカのジャズ・ジャーナリスト、マイケル・カスクーナはこう記している。“その音楽は予想していたように素晴らしい出来であった・・・。打楽器はリズムを強めたりそれを助けるばかりではなく、多彩な使われ方をしている・・・。”
 W.R.の歴史的価値を彼の言葉がいみじくも示している。ジャズのエッセンスである打楽器の魅力をたっぷりと秘め、純粋でヒューマンな音楽は、最高峰のジャズに属する。ファースト・アルバム“WEATHER REPORT”はグループとしての絶妙なバランスの元、未知の音宇宙へとつながっていく。アルバムはウェインのソプラノ・サックスとジョーのピアノからなる“Orange Lady”で開始を告げる。ピアノの弦の上、ソプラノ・サックスの音色を吹き込み、残響だけで構成した音楽。最終章のウェインのオリジナル、“Eurydice”は今も私をとりこにしている。ウェインのイメージから始まり、ヴィトウスのベースが唸る。ギリギリと突き詰める4ビート。二人のパーカションが絡みつき、皆がファンキーに歪みあい、そして、遠くの地平へと進んでいく。彼らの強力なドライブ感は1970年代前半の時代を牽引していた. W.R.の歴史的価値を彼の言葉がいみじくも示している。ジャズのエッセンスである打楽器の魅力をたっぷりと秘め、純粋でヒューマンな音楽は、最高峰のジャズに属する。ファースト・アルバム“WEATHER REPORT”はグループとしての絶妙なバランスの元、未知の音宇宙へとつながっていく。アルバムはウェインのソプラノ・サックスとジョーのピアノからなる“Orange Lady”で開始を告げる。ピアノの弦の上、ソプラノ・サックスの音色を吹き込み、残響だけで構成した音楽。最終章のウェインのオリジナル、“Eurydice”は今も私をとりこにしている。ウェインのイメージから始まり、ヴィトウスのベースが唸る。ギリギリと突き詰める4ビート。二人のパーカションが絡みつき、皆がファンキーに歪みあい、そして、遠くの地平へと進んでいく。彼らの強力なドライブ感は1970年代前半の時代を牽引していた.
ウェインは“Eurydice”を女性のセンスという形で追求している。ユリディースは全ての男性の中に存在するものであり、彼女は非常に捕らえがたい存在である。ふりかえれば逃げてしまうが、すべての人間の生活の中に漂う存在なのだ。
“風”、“女性”・・・。ミロスラフの弦の元、共同体としての音楽は静かに過ぎ去っていく。
 ◇北国にW.R.は、やって来た。オリンピックという国際的イヴェントを控え、様変わりを見せていた街。母校の前、一枚のポスターが来日公演を告げていた。 ◇北国にW.R.は、やって来た。オリンピックという国際的イヴェントを控え、様変わりを見せていた街。母校の前、一枚のポスターが来日公演を告げていた。
1971年1月12日、彼らはその演奏を披露する。ナベさんが私の代わりに足を運んだ。彼の席は1番1号38列。翌日の東京・渋谷公会堂でのライヴにはこの時の演奏がリアルに再現されている。“I Sing The Body Electric”と名づけられたこのアルバムは、ファースト・アルバムにありがちな、過剰なまでの「自意識」を捨て、本来の自分たちの目標、「前進」の実現に没頭しているかのように聴こえる。そして、W.R.に体現された“ジャズの新時代”は突然現れたのではなく、過去との因果関係を精算する作業によって達成されるという事を、この時の演奏は教えている。

今年の夏、故郷でナベさんと会いW.R.そしてウェインへと話は及んだ。音楽の詳細に加え、彼が始めて披露したエピソード。思いのほか小柄なウェインの姿と、柔和な笑顔、そしてやわらかい手。また一人の青年が、飲み物の缶をパーカションに見立て、スイングしていたこと。
近くの女性が上手に腕から下着を脱ぎ取り、投げ捨てていたことを。
W.R.のその後は今更語る事もない。彼らはアメーバーのよう、その音楽性を発展させ、ますますグループとしての融合(フュージョン)をなしていく。決定的な成熟の到来は25歳のベーシスト、ジャコ・パストリアスの加入である。彼の貢献は大き なものがあった。ロック界に旋風を巻き起こしたジミ・ヘンドリックスがエレクトリック・ギターの革命児だったように、ジャコはまさに、エレクトリック・ベースの申し子であった。アルバム、“Black Market”でW.R.の一員としてのレコード・デビューを果たしたジャコは、ジャズ・ファンを完全にノック・アウトしてしまう。やがて、W.R.はジョーとジャコのものとなっていく。 なものがあった。ロック界に旋風を巻き起こしたジミ・ヘンドリックスがエレクトリック・ギターの革命児だったように、ジャコはまさに、エレクトリック・ベースの申し子であった。アルバム、“Black Market”でW.R.の一員としてのレコード・デビューを果たしたジャコは、ジャズ・ファンを完全にノック・アウトしてしまう。やがて、W.R.はジョーとジャコのものとなっていく。
迎える“Heavy Weather”。1976年、アメリカ建国200年の年、ウェインとジョーとジャコの3人は、“Bird Land”でジャズの過去、現在、そして未来を祝福している。W.R.の魅力の全てを備えている“Bird Land”は大衆に対しジャズを高らかに歌っている。
1982年、ジャコはW.R.を脱退し、まもなく、つまらない喧嘩に巻き込まれ命を落とす。後の1986年、ウェインとジョーは、それぞれのバンドを結成し、W.R.は15年という月日にピリオドを打った。
1996年、ウェインは航空機事故で、妻のアナ・マリアを失う。
◇2004年夏、私はウェインと会った。“東京JAZZ”のPRのため、ハービーとともに生放送で演奏を披露した彼を、私は図々しくも楽屋に訪ねた。彼はハービーの後ろ、静かに微笑んでいた。かつてナベさんが遭遇したウェインと同様、小さな姿、笑み、そしてやわらかな手があった。
◇ 最後に、披露したい話がある。
“1991年8月25日、58歳の誕生日、ウェイン・ショーターはかつてのバンドリーダー、マイルス・デイビスのステージを見るためロス・アンゼルスのハリウッド・ボウルを訪ねた。バックステージに現れたウェインを見ると、マイルスは周囲の人々に、ふたりきりにしてくれ、と言った。彼は、ウェインに歩み寄り、目の前に立つと、両肩に手を置き、それまで一度も触れなかったことを語り始めた。音楽についてである。最後に、マイルスはウェインに使命を課した。「いいか。お前はもっと世に出るのだ。」伝説のトランペット奏者はウェインの両目を見据えて、力強く言った。これが彼からウェインへの最後の言葉となった。それから数週間後、マイルスは他界している。
◇9・28 今年もやって来る。
先日の12日、ジョー・ザヴィヌルの訃報に接する。便りには彼の足跡となる3人のジャズ・ミュージシャンの名が挙げられていた。マイルス、ジャコ、そしてウェイン。
今、ウェインはどこに行くのであろう。50年以上もの間、ジャズ・シーンの真っ只中にいながら、明日は何を表現するか分からない神秘的なウェインは、一瞬一瞬の中にユーモアと楽しさ、それらの深みを私たちに与えている。そして私たちになにがしかの生きる上のインスピレーションを与えてくれる。

今回の演奏は、どのような神秘を私に示してくれるのであろうか・・・。
70歳を既に越えて、今尚冒険的であり野心家であり、しなやかな想像力を発揮する無類のジャズ・ミュージシャン、ウェイン・ショーター。マイルスの高弟たちとの即興は、太いトルネードとなって、その音楽を我々に提示するであろう。
バンドの中核、ウェインの放つ音は粒子となり、スピリチュアルな輝きをもって拡散していくに違いない。集中力とテンションの高さ、しなやかに進化する音楽.
“生きる伝説”ウェイン・ショーターの音楽は、止まるところを知らない。
参照 :フット・プリンツ ~評伝ウェイン・ショーター~(ミシェル・マーサー著)潮出版社
:マイルス・デイビス自叙伝(マイルス・デイビス クインシー・トループ著)宝島社
|