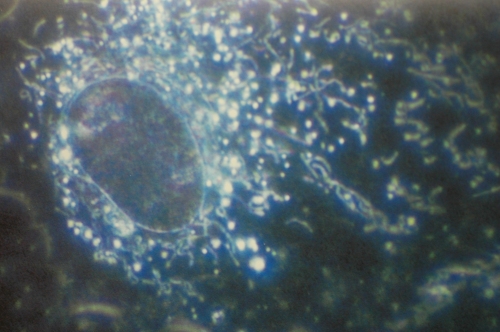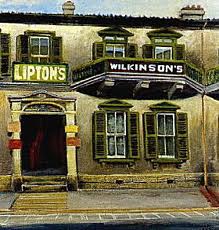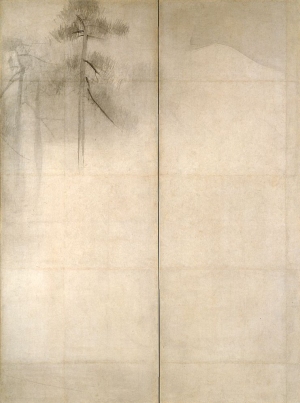スズカケノキ(鈴掛木)/スズカケノキ科スズカケノキ属プラタナスと呼ばれ、街路樹ではおなじみの落葉高木。東洋種のスズカケノキ、北米種のアメリカスズカケノキ、その2種の雑種のモミジバスズカケノキがある。30メートル以上の巨木が多く、樹皮が大きく剥げ落ち、幹にまだら模様がある。秋から冬にかけ、直径3センチ以上の果実が枝に垂れ下がる。その姿が山伏の襟にかけた白い飾りを彷彿とさせるので、鈴懸木と名づけられた。プラタナスは葉が大きいことから、ギリシャ語の「広い」という言葉に由来している。
プラタナス全般の花言葉は、天稟・天才・非凡 プラタナス(新緑)の花言葉は、天才・叡智。

▼聳える鈴懸木の下にくる。今年も冬空に、無数の実が心細げにぶらりぶらりと揺れている。この鈴懸の枝枝を駆け抜けるとき、風はさぞかし愉快だろう。風につつかれて、ざわざわと忙しく揺れる無数の実は風が過ぎ去るとともにその振幅をゆっくりと整え、ふたたび地軸に向かってまっすぐ、何事もなかったようにぶらりと垂れ下がる。

▼「公正中立について貴方はどう思っているのですか?」
先日、学生時代の先輩が編集長をするT出版社主催マスコミ志望の学生セミナーで、学生達に囲まれて質問を浴びた。
▼うまく回答ができたかどうか、自信はないが、もう一度、私の考えを整理しておきたい。私は、ある問題に対し 対立する主張あるいはイデオロギーがあった場合、Aという論陣とそれに反するBという論陣を均衡に並べて、よしとすることだけが公正中立だとは思わない。かといってAという論陣によりかかり、それを“装置”として提示することを許容するつもりはさらさらない。
▼私にとっての公正中立とは、あるテーマについて、その事の真相を組織や社会の常識にとらわれることなく自分の頭で考え抜く精神の自立を貫くことである。その悪戦苦闘のプロセスを率直に見せることが私にとっての“公共”だと思ってやってきた。
▼白か黒か、君は白派か黒派か・・・こうした思考の図式化が、これまで日本社会が育んできた行間を読みとる冗長性を切り捨てていっているように思う。私にとっての公正中立とは、白と黒の間を右往左往しながら、自分で思考し反芻するプロセスである。

▼私が取り組んできたテレビの仕事にはそう簡単には割り切れない行間のカオスをあえて引き受けるのを良しとするところがあった。言ってみれば「中庸」の視点である。中庸というと日和見主義ととらえられそうだが、孔子が唱えた中庸の徳は決して投げやりなものではない。事の真相を組織や社会の常識に囚われることなく自分の頭で考え抜く精神の自立がこの中庸という言葉には託されている。かつてテレビの現場にはこの中庸の精神を持ちあわせた職人が大勢いたように思える。
▼デジタルの時代。0か1かの二進法の世界。映るか映らないかの世界、曖昧なゴーストのない世界・・・。それと併走するかのように、世の中には二元論が蔓延しているように思う。左翼か右翼か、勝ち組か負け組か・・・わかりやすい二元論の世界に人々の思考を押し込めて安易で稚拙な行動に駆り立てようとする空気が充満している。もっと思いのままに曖昧なプロセスを漂い中庸にたどり着く多様な道筋があってもいいのに。所属は見えても個人の顔の見えない世界・・・。
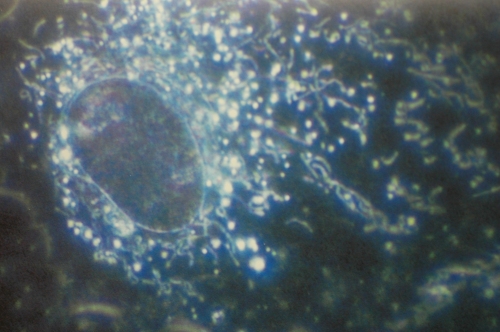
▼生物の基本単位である細胞。我々の体は60兆の細胞から構成されているが、その一つの細胞は、かつて原始の海で対立する二つのバクテリアが融合したものだ。酸素という有毒物質(太古の地球では酸素は有毒であった)を出すどう猛なバクテリアを排除するのではなく、なんとその懐に包み込んだ異端のバクテリアが生き残った。そして爆発的な進化を遂げ、今私たちの体の基本となっている。対立するものと折り合いをつけて、飲み込んでその良さをしたたかに引き出す戦略を持つものだけが繁栄を維持できる、というのが生命の基本原理である。

▼組織には、実に様々な考えや思想を持つ個性が集まっている。それぞれの個性が無数のベクトルで時代と格闘する、そのプロセスが総体として“公正中立”を奏でている。もし、この装置が二元論という図式に取り込まれて、「左翼か」「右翼か」、「保守か」「リベラルか」、「勝ち組か」「負け組か」に所属を求められ、それぞれの個性が自分という固有名詞を棄てるようなことがあれば、あっという間に、組織は機能不全に陥る。・・・・そんなことを学生に云いたかったのだが、どうもうまく伝わった気配はない。また、誤解されてしまったかもしれない。

▼鈴懸の実のように、吹き寄せる風に右往左往しながら揺れに揺れても、やがて中庸なポジションに落ち着く、そんな姿勢を貫きたい。その根底に、公のために生きるという捨て身の覚悟を持ち続けたい。
※人間のアイデンティティは選択の余地のない単一基準のものだと主張することは、人間を矮小化するだけでなく、世界を一触即発の状態にしやすくなる。突出した唯一の分類法による区分けにとって代わるものは、われわれはみな同じだという非現実的な主張なのではない。われわれは同じではない。むしろ、問題の多い世界で調和を望めるとすれば、それは人間のアイデンティティの複数性によるものだろう。多様なアイデンティティはお互いを縦横に結び、硬直化した線で分断された逆らえないとされる鋭い対立にも抵抗する。お互いの違いが単一基準による強力な分類システムのなかに押し込められれば、われわれが共有する人間性は苛酷な試練を受けることになる。(アマルティア・セン「アイデンティティと暴力」より)